退職を考え始めたとき、多くの人が悩むのが「いつ」「誰に」「どう伝えるか」ということ。
適切なタイミングと順番で退職の意思を伝えることは、円満退職のためにとても重要です。
この記事では、スムーズに退職するために知っておきたい「タイミング」と「伝える順番」のポイントをわかりやすく解説します。
関連記事➤『【保存版】転職時の退職挨拶 上司・同僚・取引先への例文とマナー』
なぜ退職を伝えるタイミングが重要なのか?
業務への影響を最小限にするため
退職は個人の自由ですが、チームや部署の業務に少なからず影響を与えます。繁忙期やプロジェクトの途中などで退職の意向を伝えると、周囲に大きな負担がかかる可能性があります。
引き継ぎ期間を確保するため
業務の引き継ぎをしっかり行うことは、社会人としてのマナーのひとつ。十分な期間を設けるためにも、余裕を持ったタイミングで伝えることが重要です。
就業規則や法律のルールを守るため
法律上は退職の2週間前までに申し出ればOK(民法第627条)とされていますが、企業の就業規則では「1ヶ月前までに申し出ること」と定めている場合もあります。
まずは、就業規則をしっかり確認しておきましょう。
退職を伝えるおすすめのタイミング
✅ 業務の繁忙期を避ける
✅ プロジェクトの区切りがついた時期
✅ ボーナス支給後など、キリのよいタイミング
✅ 就業規則に定められた期日より余裕を持って伝える
「できるだけ迷惑をかけない」「感謝の気持ちを持って辞める」という姿勢が、結果的にあなたの評価を守ります。
退職の意思は誰に、どの順番で伝えるべき?
退職の意思を伝えるときは、順番も非常に大切です。伝える相手を間違えると、社内の信頼関係を損ねてしまう可能性も。
基本の順番はこれ!
- 直属の上司
- (必要に応じて)さらに上位の管理職
- 人事・総務部門(手続き)
- 同僚・チームメンバー
同僚や人事に先に話してしまうと、「順番を飛ばされた」と上司が不快に感じることがあります。退職の意向は、まず直属の上司に直接伝えるのが社会人としての基本マナーです。
上司には「相談ベース」で伝えるのがポイント
退職の意思を伝える際は、いきなり「辞めます」と切り出すのではなく、
「少しご相談したいことがあるのですが」と相談ベースで始めるのがベターです。
そうすることで、相手も心の準備ができ、話し合いがスムーズに進みやすくなります。
また、感情的にならず、冷静かつ丁寧な姿勢を意識することも忘れないようにしましょう。
タイミングと順番を間違えると、こんなリスクも…
❌ 引き継ぎが間に合わず、職場に迷惑をかけてしまう
❌ 上司の顔をつぶし、評価が下がる
❌ うわさで退職が広まり、人間関係が気まずくなる
❌ 最後に悪印象を残し、転職先にも影響が出る可能性
「辞めるから関係ない」と思わず、最後まで社会人としてのマナーを守ることが大切です。
まとめ:円満退職を実現するために
退職を伝える際には、タイミングと順番が非常に重要です。
余裕を持って計画的に行動することで、スムーズかつ円満に退職することができます。
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| ✅ タイミング | 業務の区切りや就業規則を考慮 |
| ✅ 順番 | まずは直属の上司に伝える |
| ✅ 話し方 | 相談ベースで冷静に伝える |
| ✅ 引き継ぎ | 丁寧に、責任をもって対応する |
退職は次のキャリアへの第一歩。
円満に職場を去ることで、気持ちよく新しいスタートが切れるはずです。
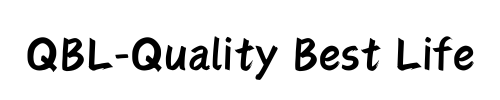
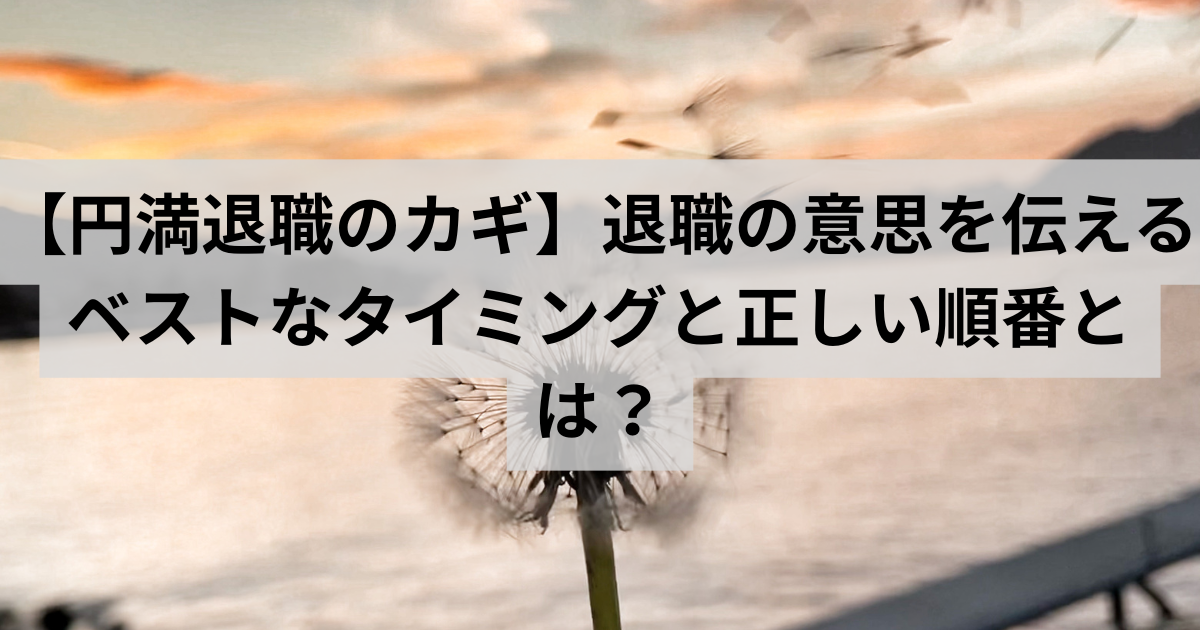
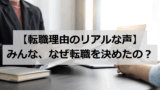
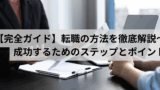
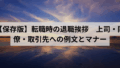
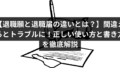

コメント